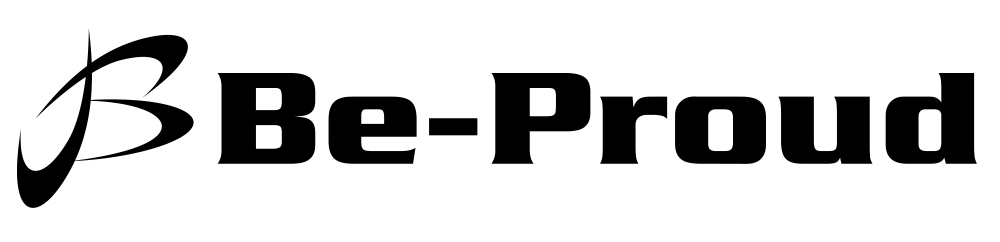こんにちは、新百合ヶ丘のパーソナルジム Be-Proudです。
「1日1400kcalに抑えているのに、なぜか痩せない…」
「なぜ、こんなに頑張っているのに痩せないんだろう…」
そんな疑問や焦りを感じていませんか?
毎日1400kcalという食事量をしっかり守っているのに、体重はピクリともしない、あるいはむしろ増えていく――。そんな焦りや不安を抱えているあなたは、決して一人ではありません。
ダイエットでは「摂取カロリー < 消費カロリー」が基本原則ですが、実際には数字だけではうまくいかないケースも少なくありません。
その背景には、「栄養バランスの偏り」「消費エネルギーの低下」「ホルモンや生活習慣の影響」など、複数の要素が関係しています。
この記事では、「1400kcalに抑えているのに痩せない理由」を10年以上トレーナーとして現場で指導している経験に基づいて5つのパターンに整理しながら、あなた自身の状況と照らし合わせてチェックできる構成で解説します。
「もうどうすればいいか分からない…」と諦める前に、ぜひ最後まで読んで、あなたのダイエットを成功へと導くヒントを見つけてください。
そもそも「1400kcal」は、あなたにとって本当に合った数字か?
「食事量を抑えよう」として、1400kcalという数字をなんとなく設定していませんか?
- 昔それで痩せた経験がある
- SNSやネット記事で見かけたから
- コンビニの“ダイエット用弁当”がそれくらいだったから
たしかに1400kcalという量は“少なめ”の印象を受けますが、それが「あなたにとって適切かどうか」は別問題です。ここで一度、「自分の体が1日にどれくらいのエネルギーを使っているか」を見直してみましょう。
自分の“消費カロリーの目安”を知ろう
| 項目 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 基礎代謝 | 寝ていても心臓や呼吸などで使われるエネルギー | 女性:1200〜1300kcal / 男性:1500〜1700kcal |
| 活動による消費 | 歩く・立つ・家事・通勤・運動など | 200〜600kcal以上(生活スタイルで差) |
| 食事による消費 | 食べ物を消化・吸収するときに使うエネルギー | 食事量の約10% |
📐 計算式でチェック!
以下は、性別・年齢・体型で消費カロリーを推定する式です
- 女性:655.1+(9.56×体重kg)+(1.85×身長cm)−(4.68×年齢)
- 男性:66.5+(13.75×体重kg)+(5.0×身長cm)−(6.76×年齢)
計算例:
- 女性(40歳・158cm・56kg)→ 約1295kcal
- 男性(35歳・175cm・72kg)→ 約1630kcal
💡 さらにライフスタイルを加味すると?
| ライフスタイル | 係数 | 消費カロリー目安(※例より) |
|---|---|---|
| 座りがち | ×1.2 | 女性:1554kcal / 男性:1956kcal |
| 日常的に動く | ×1.5〜1.6 | 女性:約1950kcal / 男性:約2450kcal |
| 運動習慣あり | ×1.75〜1.9 | 女性:2200kcal以上 / 男性:2800kcal以上 |
もっと簡単に知りたい人は
- 体重×30:かなり控えめな生活
- 体重×35:軽く動いている人
- 体重×40:運動を習慣にしている人
例:56kgの女性 → 1680〜1960kcal
72kgの男性 → 2160〜2520kcal
あなたにとっての「1400kcal」は適切ではないかも?
こうして見ると、「1400kcalなら絶対に痩せる」とは限らない理由が見えてきます。
- 活動量が少ないと、1400kcalでは消費カロリーを上回らず痩せにくい
- 代謝が落ちている人では、1400kcalすら多い可能性も
「1400kcalは少ないはずなのに…」と感じている方は多いですが、実際には「体にとって必要な量を下回りすぎて代謝が落ちている」、あるいは「消費カロリーが思ったより少なく赤字が出ていない」というケースも少なくありません。
まずは“自分の1日の消費量”を見直すことが、正しい食事設定の第一歩になります。

1400kcalでも痩せない5つの主な原因
原因①:カロリーは守れても栄養は不足?PFCバランスの落とし穴
1400kcalに抑えているのに痩せない…
そんなとき、見直してほしいのが「何を食べているか=栄養のバランス」です。
たとえば、あなたの食生活にこんな傾向はありませんか?
- 極端な糖質制限(ご飯・パン・芋類をほぼカット)
- 野菜中心で主菜が少なく、たんぱく質が足りない
- サラダ+スープで済ませることが多い
- 脂質を避けすぎて、オイルや魚の脂も取らない
- プロテインだけに頼り、食事の内容が薄い
- 調味料や飲み物に含まれる“隠れ糖質・脂質”を見逃している
カロリーが低いからといって、栄養まで足りているとは限りません。
とくに「PFCバランス」が偏っていると、体は思うように変わらなくなってしまいます。
PFCバランスとは?
| 栄養素 | 役割 | 理想的な比率(例) |
|---|---|---|
| たんぱく質(P) | 筋肉・代謝維持 | 約20〜25% |
| 脂質(F) | ホルモン・細胞・吸収補助 | 約20〜30% |
| 炭水化物(C) | 主なエネルギー源 | 約45〜55% |
▶ 1400kcal/日(女性・軽運動あり)モデル例
- たんぱく質:約70g
- 脂質:約39g
- 炭水化物:約193g
これを大きく下回る/偏ると、次のような悪循環を引き起こします。
栄養不足が引き起こす3つの落とし穴
- 筋肉の減少 → 代謝の低下 → 痩せづらく太りやすい体に
とくにたんぱく質不足+糖質カットは筋分解が進みやすく、基礎代謝が下がります。 - ホルモンバランスの乱れ → 生理不順・肌荒れ・情緒不安定
脂質が足りないと、女性ホルモンやレプチン(食欲抑制)などの働きに影響が出ます。 - 強い空腹感・ドカ食い → メンタル低下とリバウンドのリスク
エネルギー不足で脳が飢餓状態と判断し、「我慢できない食欲」に襲われることも。
解決のためにできること
炭水化物は「質」で選ぶ」
白米より玄米、精製パンより全粒粉。低GIで血糖値を安定させ、空腹感を抑えます。
まずは「食事の記録」から始める
MyFitnessPalやあすけんなどのアプリを使って、2〜3日分のPFCを見える化しましょう。
→ 思っている以上に「脂質ゼロ・糖質少なすぎ」の偏りが多く見つかります。
たんぱく質は毎食「手のひら1枚分」
肉・魚・卵・大豆などを意識的に取り入れて、筋肉と代謝の維持を図りましょう。
“良い脂”をしっかり摂る
ナッツ・アボカド・青魚・亜麻仁油など、不飽和脂肪酸を大さじ1杯分が目安です。

「同じ1400kcal」でも、中身が変わるだけで体の反応はまったく違います。
Be-Proudでも、PFCバランスを見直しただけで停滞を打破した方がたくさんいます。
数字だけではなく、「体がよろこぶ食事」を。
まずはそこから始めてみましょう。

原因②:頑張っているのに消費が足りない?基礎代謝と活動量の見落とし
1400kcalという食事量は、「頑張っている」と言える水準です。
しかし、1日に体が使うエネルギー(消費カロリー)が1400〜1600kcal前後しかないような生活を送っている場合、食べた分と使う分がほぼ同じで、赤字になっていない可能性があります。
摂取量と消費量が拮抗していませんか?
以下のような生活になっていませんか?
- デスクワーク中心で1日の歩数が3000歩未満
- ほとんど座りっぱなし、移動も車やエスカレーター
- 運動は週に1回以下、もしくはゼロ
このような生活では、基礎代謝+日常活動での消費エネルギーが合計1400〜1600kcal程度にとどまることがあります。
つまり、「1400kcalに抑えているつもり」でも、実は“ちょうどプラマイゼロ”か、少し余っている状態かもしれません。
日常の行動で消費できるカロリー(30分あたり)
| 活動内容 | 消費カロリー(体重55〜60kgの場合) |
|---|---|
| ゆっくり歩く(散歩) | 約80〜100kcal |
| 通勤レベルの歩行 | 約110〜130kcal |
| 階段の上り下り | 約150〜170kcal |
| 家事(掃除・洗濯など) | 約90〜120kcal |
| スクワット10分(断続的) | 約50〜70kcal |
なぜ痩せない?「動いていないわけではない」の落とし穴
多くの人は「仕事で忙しいから、けっこう動いてるはず」と思いがちですが、“忙しさ”=“消費カロリーが多い”とは限りません。
- 通勤でも「バス→エスカレーター→オフィスで座りっぱなし」では運動量はほぼゼロ
- 家事をしていても、“移動の少ない同じ空間内”では消費はごくわずか
- 筋トレや有酸素運動がなければ、筋肉は刺激されず、代謝は上がらないままです
今すぐできる「消費量アップ」の工夫
- 1日6000歩以上を目安にする(スマホの歩数計アプリなどで管理)
- 階段を選ぶ習慣をつける(移動ついでの代謝UP)
- 朝か夜に5〜10分の軽い運動(ストレッチ・体操など)を取り入れる
- 「1時間座ったら1回立つ」を意識する
- 週2回以上は、“運動をする日”を予定に入れておく

カロリーを減らすことばかりに目がいきがちですが、実は「どれだけ使っているか?」がボトルネックになっているケースも非常に多く見られます。
まずは日常生活の中で“燃やす習慣”を。
体を少しずつ「使う体」に変えていくことで、同じ食事内容でも結果が大きく変わってきます。
原因③:体が“省エネモード”に?停滞期を招くホメオスタシスの罠
「食事も運動も頑張ってるのに、突然まったく体重が落ちなくなった…」
それ、あなたの努力が足りないのではなく、体が“順応”しているサインかもしれません。
ホメオスタシス反応とは?
人間の体には、変化から身を守る“防御システム”が備わっています。これがいわゆる「ホメオスタシス(恒常性維持)」です。
ダイエットでは、「カロリーが減り続ける=飢餓状態」と判断し、体が“省エネモード”に切り替わってしまうことがあります。
省エネ状態になると起こること
| 変化 | 内容 |
|---|---|
| 基礎代謝の低下 | 筋肉の働きが抑えられ、消費エネルギーが減る |
| 体温の低下 | エネルギーを節約するために熱産生が落ちる |
| 食欲の増加 | グレリン(食欲ホルモン)が活発に分泌される |
| 脂肪燃焼の抑制 | レプチン(満腹ホルモン)が低下し、脂肪の分解が進まなくなる |
| 排出機能の低下 | 便秘・むくみなどが起こりやすくなる |
停滞期に「さらに減らす」は逆効果
体重が止まったからといって、
- 摂取カロリーをさらに削る
- 運動を急に増やす
などの対応をすると、かえって体にとっては“緊急事態”としてさらに守りが強くなります。
その結果、脂肪をもっと溜め込みやすくなり、ストレスでホルモンバランスも乱れやすくなります。
停滞期の正しい乗り越え方
食事の“質”を高める
→ 無理に減らさず、栄養バランス(PFC)と食材選びに注目を
「今、体が順応している」と冷静に受け止める
→ これは失敗ではなく、変化が定着しようとしている“過程”です
急がず、2〜3週間は現状のまま維持を意識する
→ 安定した生活リズムが体に安心感を与え、代謝が戻りやすくなります
睡眠・休息の質を見直す
→ 成長ホルモンやレプチンなど、代謝を高めるホルモンは「休んでいるとき」に分泌されます
食事の“質”を高める
→ 無理に減らさず、栄養バランス(PFC)と食材選びに注目を

ダイエットは、「止まらずに減り続ける」ものではありません。
体には“適応のための準備期間”が必要です。
だから、停滞=悪いことではなく「変化の前触れ」。
体の声に耳を傾けて、焦らずじっくり、次のステップに備えましょう。

原因④:隠れた敵?ホルモン・ストレスがダイエットを妨げるメカニズム
ストレスや睡眠不足は、ダイエットに深刻な影響を与えます。
ホルモンの例とその影響
前の章で、体には“飢餓から守る仕組み”=ホメオスタシスがあることをお伝えしました。
この生理的な反応に大きく影響を与えるのが、ストレスとホルモンバランスです。
食事や運動を頑張っていても、「気づかぬうちにホルモンが“痩せづらい状態”をつくっている」ケースは少なくありません。
ストレスがダイエットに与える影響
慢性的なストレス状態になると、体内でコルチゾールというホルモンが多く分泌されます。
コルチゾール(ストレスホルモン)の働き
- 脂肪の蓄積を促す(特に内臓脂肪)
- 血糖値を不安定にし、間食欲を強める
- 筋肉の分解を進め、代謝が落ちやすくなる
つまり、「頑張っているのに太る」状態の裏には、ストレスの積み重ねがあることも。
睡眠不足と“太りやすさ”の関係
睡眠時間が6時間を切るような生活では、以下のような変化が起こります。
| ホルモン | 正常時の役割 | 睡眠不足での影響 |
|---|---|---|
| レプチン | 満腹感を伝える | 分泌が減って食欲が増す |
| グレリン | 空腹感を高める | 分泌が増えて過食傾向に |
| 成長ホルモン | 脂肪分解・代謝促進 | 分泌が減って脂肪燃焼が鈍る |
また、睡眠の質が悪いと、自律神経が乱れ、腸内環境やホルモン分泌のリズムにも影響します。
起きやすい悪循環の例
- ストレスで甘いものやジャンクフードを欲する
- 食べたことへの後悔 → さらにストレス
- 寝つきが悪くなり、翌日また過食傾向に
→「自分を責める→さらに悪循環へ」のスパイラル
改善のヒント:ホルモンを整える生活習慣を
- 睡眠は6.5〜7.5時間を目安に確保
→ 寝る1時間前はスマホを見ない/照明を落とすなど準備を - ストレスを“抜く習慣”を持つ
→ 深呼吸・散歩・音楽・入浴・趣味など、“頭を空にできる時間”を1日15分だけでも - 軽い運動で「脳の回復スイッチ」を入れる
→ ストレッチやウォーキングで、副交感神経を優位に

痩せるためには「食事と運動」だけでなく、“心とホルモン”の状態を整えることも重要です。
目に見えない部分だからこそ、意識してケアしていきましょう。

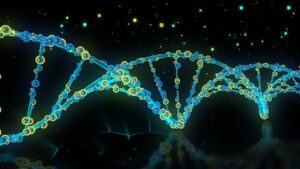
原因⑤:焦りは禁物!期間が短すぎる「体の適応未完了」のサイン
「ダイエット始めたのに、1週間経っても体重がまったく動かない…」
このような焦りは、多くの方が一度は経験します。ですが、それは失敗ではありません。
むしろ、体が変化に“適応する準備”をしている段階であり、見た目や数字に現れない期間こそ重要です。
体の中で起きている「準備段階」
取り組みを始めた直後、体の中では次のようなことが起きています:
- グリコーゲン(糖質+水分)の調整
→ 体内の水分バランスが変わり、一時的にむくみが増えることも - ホルモンの再調整(レプチン・インスリン感受性の変化)
- 脂肪と筋肉のエネルギー利用の再構築
→ 使われるエネルギー源が変化し、最初は不安定 - 腸内環境・自律神経の変化
→ 食生活や生活リズムの影響で腸の動きや排出にも変化が
これらの変化は、2〜4週間ほどの“助走期間”が必要です。
すぐに成果が出なくても、それは「まだ変化が見え始めていないだけ」なのです。
むしろ一時的に「体重が増える」ことも
特に運動を始めた直後には、筋肉に微細な炎症や水分保持が起こるため、一時的に体重が増えるケースもあります。
- 「動いているのに増えた」→ 落胆しやすいが、これは回復のサイン
- 「頑張っているのにむくむ」→ 体が順応中なので自然な反応
適応期に意識したい3つのこと
- 体重以外の変化にも目を向ける
→ 気分・便通・肌の調子・姿勢・疲れにくさなど、体は静かに変わり始めています - 数字に一喜一憂しすぎない
→ グラフで“週単位”の傾向を見ることで、冷静さを保ちやすくなります - 最初の2週間は“整えること”に集中
→ 食事・睡眠・活動量を無理なく整えることが、後の変化を大きくします
「結果が出る前にやめてしまう」それが一番もったいない
多くの人が「あともう少し続けていれば変わり始める」というタイミングで諦めてしまいます。
でも、Be-Proudに通うお客様の多くも、「最初の2週間はほとんど体重が変わらなかった」と話しています。
継続こそが、変化のスタートライン。
適応を信じて、まずは生活リズムを整えるところから始めましょう。
あなたの状況別「やるべき見直し」
パターンA:運動ゼロ/デスクワーク中心
- 1日3000歩未満の人はまず歩数を増やす(目標:6000歩以上)
- 通勤や買い物では階段を使い、座り時間が1時間続いたら一度立ち上がる
- たんぱく質は毎食20g前後を意識して摂取し、筋肉の維持を図る
パターンB:週2〜3の軽い運動あり
- PFCバランス(たんぱく質・脂質・炭水化物)の比率を見直す
- 糖質を減らしすぎていないか、脂質が過剰でないかをチェック
- 筋トレと有酸素運動を交互に取り入れて「刺激の変化」を与える
- 睡眠・水分・ストレスなどの“見えない影響”も意識する
パターンC:食事も運動も頑張っているのに停滞
- 体重や見た目だけでなく、気分・意欲の変化なども振り返る
- 睡眠時間が6時間未満になっていないかを見直す(質にも注目)
- 一時的な停滞期と捉えて、2〜4週間の継続で変化を待つ
あなたに合ったダイエット、Be-Proudで見つけませんか?
Be-Proudでは、運動初心者専門ジムとして、一人ひとりの体質・生活リズム・悩みに合わせた「パーソナルサポート」を提供しています。
- PFCバランスの組み立て方
- 継続できる食事と運動の設計
- モチベーションが続く環境づくり
どれも、自分ひとりでは難しいことかもしれません。
だからこそ私たちが、あなたの変化を支える“伴走者”になります。

新百合ヶ丘でパーソナルジムをお探しなら、運動初心者専門のBe-Proudへ!
完全個室×マンツーマン指導で、無理なく続けられる運動習慣をサポートします。
一生モノの健康づくりを、今こそ始めてみませんか?